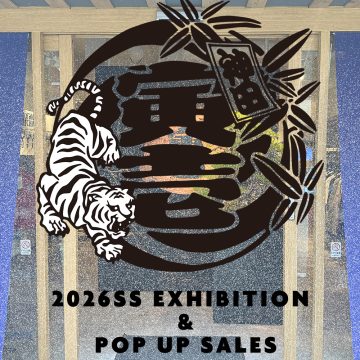寅壱、運命の数字”2530″。
“2530”。
それは寅壱にとって運命の数字だ。
この2530は所謂、生地の番号なのだがこの生地が寅壱の鳶を中心としたワークウェアに採用されてから独自の発展を遂げ出した。
2530はいつどのようにして生まれたのか?
この生地が生まれたのは、およそ50年ほど前と言われている。
ちょうど日本は高度成長期の真っ只中であり、建設ラッシュを迎えた頃だ。爆発的に現場が増えていく中で、同時に多くの職人が新たに生まれた。
新しい時代の作業着というものがまだ多くなく、数多くの当時の工事現場の中で職人たちの要望で圧倒的に多かったのは、「快適性」「頑丈さ」「防塵性」だった。
快適性については、裾を始め全体的にゆとりを持たせることで肌(特に膝)にまとわり付かないようにして解決策を探った。そして頑丈さは当時でも頑丈な生地を使用し対応をしていた。言い換えると、ニッカズボンの誕生そのものがこの背景から生まれ、鳶職人のニーズに応えていた。
だが、一番の問題は「防塵性」だった。
日々、砂埃と煤にまみれた建築現場では、呼吸器官に対しては、マスクを着用するなどの対策が練られていたが、それ以外に、汚れ、特に煤汚れなどはどうしようもなかった。
ここは職人たちの強い要望として、「埃がつかない作業着はないものか?」という問い合わせが常にあったようだ。
そうした中、当時は生地にカーボン素材を通すことで防塵対策となっていったが、寅壱ではもう一歩、「練り込む」ところまで踏み込んでいった。
結果、数ある品番の中で最も頑丈さと防塵対策に絶大な効果を発揮したのが2530だった。
—–しかしこれだけでは、当時の寅壱の代名詞なるまでには行かない。性能だけでは「粋」だったりするところ、すなわち「カルチャーとしての要素」までには届かないのだ。
だが、その後鳶職人に絶大な人気を得るに至ったのには二つの要因が考えられる。
一つは鳶職人の時代背景だ。
明治時代以降の鳶職人は「消防士」的な意味合いは薄れていき、足場鳶人の原点に戻っていた。また、ゼネコンなどが生まれ建設業も大企業化する中、鳶職人の多くは組織というよりも、個人事業主が多かった。この「個人事業主が多い」という背景は江戸時代の火消し鳶のイメージと被り「粋」「いなせ」「男」というイメージを個々の個人事業主がリンクさせることとなる。ここにカルチャーとしてのベースができることになる。
二つ目は色展開だ。
こうした個人事業主の鳶職人は、粋であることがライフスタイルの一つにまでなっていったが、横並びが進む中、鳶職人同士で差別化を図りたくなってきたのが当時だった。
そこで寅壱が行ったのは40色近い色展開だ。鳶職人のコミュニティの中で「差別化をしたい」というニーズに応えたのが寅壱であり、もともとデザインによる「快適性」、生地の「頑丈性」とカーボンを練りこむことにより生まれた「防塵性」を備えた2530によるニッカズボンがある中でカラーバリエーションを(やたらと)増やすことにより、爆発的に鳶職人の中心へと入っていったのだ。

その後、「寅壱は作業着のアルマーニ」と呼ばれたり、「寅壱を着ていたら瀬戸大橋の工事現場からは落ちない」など、様々な都市伝説も生まれてくることとなる。
そして現在、鳶装束と2530はワークウェア文化の重要要素の一つとして、様々にファンを増やしていっている。
こうこうした時代背景から生まれた少し光沢のある素材感や、独特なシルエットがモード的な解釈を受けて花開くのも、根底に流れるのは鳶職人がサンプリングをした日本文化の「粋」や「いなせ」だったり、「男の装束」といったところであるもの面白ところだ。
現在進行形で続く今の時代、さらにこうしたプロセスを経て、日本の作業着文化も多様性を帯びてくるのであろう。